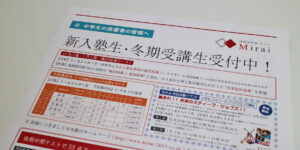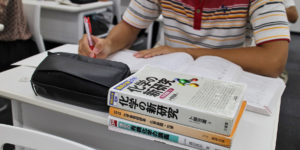先日のブログに続き,進研模試結果の続編です。
まずは高1生。高2生に負けじとなかなかの結果を残しています。
7月実施の進研模試の数学で85点 (全国偏差値は74.2),今回は86点 (全国偏差値は73.6)。なお,これは岐阜高や岐阜北高ではなく,長良高の生徒が残した結果です。
校内では当然連続して 1位で,県内でも100位台。定期テストでは90点台後半は当然で,満点をとってくることもあります (もちろん過去問や予想問題なし)。
この生徒は以前のブログでも紹介したことがありますが,彼は『赤チャート』をこよなく愛し,それを楽しそうに自習室で取り組み頻繁に質問してくれます。
結果もある程度順調に出ていますし,目標を持って取り組んでくれていますから私も静観しているといった感じです。これからも,より突き抜けるべく頑張ってほしいです。
続いて写真の生徒 (高2生・理系) も,これまでの 4回の進研模試で英語・数学・国語の 3科全国偏差値において平均して 73.5 という結果を残していますが,理科・社会も頑張っています。
在籍する岐阜高でもほぼ毎回上位です。日頃から努力を積み重ねて頑張っていますし,科目を問わず質問も頻繁にしてくれます。まさに,出るべくして出た結果と言えます。
もちろん,これまでのブログでも散々述べてきたように,過去問や予想問題の類を駆使して残した結果ではなく,環境をうまく使い熟した生徒の頑張りによる結果です。
以前のブログでも紹介したように,当塾の集団指導コースの高2生は文系は全員,理系は 3名が日本史選択です。
現在は特講でのみ授業を行なっており,日頃は山川出版社の『書きこみ教科書』に取り組ませてコツコツと基礎をつくらせています。
なお,現高3生のセンター試験当日 (2016年 1月16日) からは授業を毎週実施に切り替え,7月には現代史まで完了するカリキュラムで指導します。
私も理系の日本史選択でしたが,教科書と用語集を用いてしっかり学んでおけば,自身の経験からもセンター試験の問題レベルであれば容易に正解できると思います。
と言うより,奇を衒った問題集や参考書の類は不要です。どの科目にも共通していることですが,まずは基礎をしっかりと固め,以降は “偏りのない精選された問題集” に取り組みます。
物理で言えば数研出版の『重要問題集』または『リードα』を一通り熟して,河合出版の『良問の風』,『名問の森』といった問題集に取り組む。これに尽きます。
基礎が固まっていない状態で『良問の風』はまだしも『名問の森』に取り組むのは明らかに無謀でしょう。
繰り返しになりますが,本格的な受験対策に入るまでにいかに基礎を固めることができるか。私たちはとにかくこれを追求し,塾生たちに徹底させることに力を注ぎます。
だからこそ私たちは安易に過去問を与えない,予想問題に頼らせない。その場凌ぎ,または急場凌ぎを繰り返したところで長い目で見た学力が身につかないことを知ってるからです。