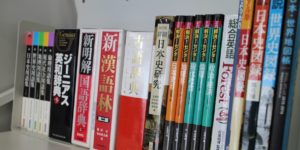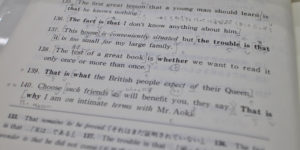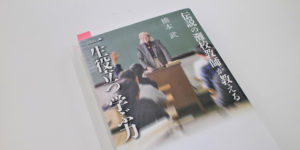現在,私は小5生から高3生までの英語科の集団指導と個別指導を担当しており,2015年 9月時点で中高生に対する指導歴は18年 6ヶ月,小学生に対しては16年 6か月となりました。
私は一貫して “例文主義” であり,確たる語彙力と文法知識なくして真の英語力は身につかないと考えております。
それらをベースとして “多読” と “多聴” を繰り返すとともに,書く・話すなどの “発信” も繰り返すことで揺るぎない英語力を獲得させる。
時間はかかりますが,これが私の考える英語科指導のゴールであり,大量の問題演習を通して身につく各種試験等に特化した薄っぺらい英語力とは一線を画するものです。
それが可能なのは,最長で 8年間にわたって指導ができることが何より大きいのだと考えます。
当塾に在籍する高3生の中にも私の指導を受けるようになって 8年目という生徒がおりますし,高2生に目を向けても 7年目という生徒が結構います。
中学・高校の 6年間というパターンも多く,当塾を推薦する声を寄せてくれている京都大に進学した櫻井くん,名古屋大に進学した河合くんも同様に 6年間です。
数回の連載で,私の英語科のステージごとの指導方針や授業の進め方に関して綴ろうと思います。
第1回目となる今回は,小学生の英語科指導に関して綴ります。
小学生は小5生・小6生のみ英語科の集団指導コースを開講し,月2回の指導を行なっております (小学生は英語科の個別指導コースは開講しておりません)。
英語科の指導が専門ではありますが,小学生の間は英語よりもむしろ国語の学習や読書のほうがはるかに重要であるというのが私の意見です。これはまた別の機会に綴ることにします。
英語に関してあくまで中学入学準備と位置付けて単語や英文を繰り返し書き,発音して,英語に慣れてもらおうというのが狙いです。
例えば小5生であれば,2年間をかけて中1生の履修内容を網羅するイメージです。現在の小5生は,小6生の 1月に英検 5級を受検してもらおうと考えております。
熱心な方からは「小6生の 1月で英検 5級は遅いのではないか」などと聞こえてきそうですが,私は単語や文法知識が固まっていない状態で英検を受検し続けてもあまり意味がないと考えます。
もちろん,次々と級を取得することで大きな自信になるでしょうし,英語が好きになる等のメリットも考えられますから,その頑張りを否定するつもりはありません。
しかし,ライティング (書き取り) のないマーク式の解答方式ですし,スピーキング力の問われる二次試験のない英検 4級までは「なんとなく」で合格できてしまうことも事実です。
例えば英検 4級であれば比較の単元が出題されますが,穴埋め問題で解答欄の直後に than があれば,「おそらく -er か more の付いているこれだな」と解答できてしまいます。
比較級をつくる際,どういう場合においては形容詞または副詞に more が付されるのか,または er が付されて語形が変化するかはここでは問われていないわけです。
さらには than の品詞は何なのか。こういったことにも関心を持って辞書等で調べて理解することが学習の本質であり,ただただ暗記すればよいというのは寂しい限りです。
than は中2生で習う when や because と同じく副詞節を形成する接続詞ですが,これを知ろうともせず直後に人称代名詞ならとりあえず主格を放り込むという解法が罷り通っているのです。
つまり,過去問等をある程度熟してさえいれば,背景知識が少々足りなくも正解できてしまうというところが問題であり,漢字のように “読めるけれども書けない” と似た状態に陥ってしまうのです。
小学生で英検 3級や 4級を取得できていても,中学生で明らかにライティングの力が不足しているケースが私のこれまでのキャリアにおいても見られました (もちろん全員ではありません)。
こういうことからも,私は各級で求められる知識,例えば英検 3級を例にとると関係代名詞や間接疑問文まできっちりと学んでもらったうえで受検させる方針を貫いております。
漢字検定と同様に,私は英検に関しても『受検するならば満点で』という考えを持っています。
なんとなく,または過去問や類題を熟すことで合格したケースでは,先日のブログでも取り上げたように本当の意味での達成感は得られないばかりか,英語力は身についていないのです。
“日常生活において使わない言語” だからこそ丁寧に。
さらには,リーディング・ライティング・リスニング・スピーキングの 4技能をバランスよく鍛えることが,真の英語力,つまり “使える英語” にしていくためには重要なのです。