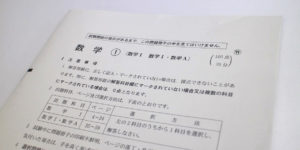12月28日(火) から30日(木) の日程で,中3生から高3生を対象に『冬特講 2021』を実施しました。
『冬特講』は当塾の開塾年である2015年から毎年実施しており,今回が通算 7回目の実施となります。
今年も高い志を持った多くの受講生が,各々の目標を持って授業に臨んでくれました。



『冬特講』は中3生が高校入試に向けた講義および演習,高1生から高3生が大学入学共通テストに向けた各科の演習および解説を実施する集中講義です。
中3生と高3生は初日⋅ 2日目が10時から22時の12時間,最終日は10時から18時の 8時間にわたって学び,3日間の合計は32時間に達します (高1生と高2生は 2日間で17時間)。
開塾した年から『冬特講』のタイムスケジュールは変更しておらず,受講生たちは各種娯楽から切り離された “学びに集中できる時間” を過ごすことになります。

昨年は新型コロナウィルス感染拡大状況を鑑みて来客を断りましたが,今年は数名の来客を迎えました。
向かって左の男性はこれまでのブログでも何度か登場してもらっている教え子で,私とはもう17年の付き合いになります。
小5生から高3生までの 8年間を生徒として,大学・大学院の 6年間をアルバイト講師として私と関わり,社会人になって 3年目の現在も私と食事やゴルフを共にする間柄です。
彼は来春に結婚式を挙げるとのことでお招きをいただいており,乾杯のスピーチを依頼されました。
教え子の結婚式に出席するのは 2年半ぶりとなりますが,このような席に招待してもらえることはとても幸せなことです。
向かって右の女性は名古屋大に進んだ当塾の 2期生で,大学卒業までの 4年間はアルバイト講師として力を貸してくれた可愛い教え子です。
彼女も小4生の終わりからと私とは13年の付き合いがありますから,その成長を具に見てきたという意味で,社会人として活躍してくれている今の姿を非常に誇らしく思います。
小学生の頃から指導してきた教え子が受験を経て成長し,大学卒業後もこうして成長した姿を見せに来てくれることが何より嬉しいです。
以前のブログでも触れたように学校ではこうはいきませんし,彼らには今後も多くの人の幸せために,そして世の中の発展のために頑張ってほしいと願っています。

続いて大学1年生 (いずれも当塾 6期生) の 2名で,昨年までは生徒として『冬特講』を受講し,この春からそれぞれ上智大,名古屋大へ進みました。
向かって左が上智大へ進んだ教え子で,夏に続いて顔を出してくれました。
受験生だった今春までは毎日のように顔を合わせていたのに,東京へ出て以降はこうして長期休暇の際に再会する形になりましたが,その分いろいろな面での成長が感じられます。
学業成績も順調で課外活動も熱心に取り組めているとの報告を受けていますから,彼女の今後の成長と活躍にも期待しています。
向かって右は名古屋大に進んだ教え子で,現在は当塾のアルバイト講師として高校生の指導 (主に生物・化学) にあたるなど力を貸してくれています。
彼女も小学生だった頃から大学合格まで指導してきた教え子ということもあって,塾生の指導にあたっている姿を見ると感慨深いものがあります。

2021年の授業も『冬特講』をもって無事に終了することができました。
当塾は 2021年 3月に開塾から 8年目を迎えます。保護者の皆様ならび地域の皆様をはじめ,当塾を支えてくださる多くの方々に感謝致します。
いつも本当にありがとうございます。
最後に,当塾の関係者から誰一人として新型コロナウィルス感染者が出ていないことは本当に幸運なことだと思います。
当塾は今後も感染拡大防止に向けた各種取り組みを緩めることなく実践します。