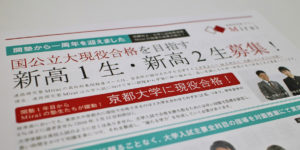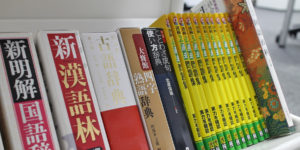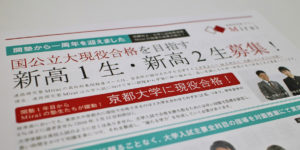
3月21日(月・祝),中日新聞にチラシを折り込みます。
今回のチラシは当塾が大学受験を見据えた指導に力点を置いていることを強調し,これまでは行なわなかった高校生の新入塾生募集を前面に打ち出したものです。
進路探究塾 Mirai は小5生から高3生を対象に各種指導を行なっております。
どの学年においても子どもたちが目標を持ち,日々コツコツと取り組む習慣をつけ,学習を愉しむ姿勢を育む。これが進路探究塾 Mirai の目指すものです。
知識を身につけ,それを長い時間をかけて熟成し,“確たる学力” を形成していく。
例えば定期テストの過去問または予想問題といった “安易なもの” や “お手軽なもの” を徹底的に排除し,「これさえやれば得点アップ!」的な指導を一切行わないのが当塾の指導です。
そういったものに熱心に取り組んで得た得点は “虚像” である可能性が高く,当塾の方向性とは全く逆行するものです。

ここのところ新高1生と新高2生のお問い合わせが続いているため,今回のブログでは改めて当塾の高校部を紹介します。
先日のブログと重複する内容も多いですが,説明をより詳しくしたものもありますので併せてお読みいただけると幸いです。
当塾の高校生集団指導コースは一般入試を経て国公立大や難関私大への進学を希望する高校生に限定し,1学年あたりの定員は16名です。
在籍先の高校も限定させていただいており,それ以外の高校の場合は当塾が定める基準をクリアしていることに加え,推薦入試で大学進学しないことを条件に受講していただいております。
以前のブログでも申し上げましたが,当塾の高校生集団指導コースでは学校準拠指導および推薦入試対策は一切行ないません。
高校生個別指導コースは私立中高一貫校に通う生徒または国公立大を受験しない生徒を対象としており,在籍生からの紹介状をお持ちの方のみ入塾を受け付けている状況です。
なお,1学年あたりの上限数を 4名と設定しているため,新高1生はあと 1名,新高2生はあと 2名,新高3生は上限に達しているため受付停止中となっております。

新高1生の保護者の方からのお問い合わせの際,「高校受験まで通っていた塾は高校生のコースが開講されていない」というお声が数件ありました。
確かに高校生指導,中でも難関大を志望する受験生指導はおいそれと熟せるものではありませんし,まず入試に必要な全科目の教員を揃えることが難しいということなのでしょう。
先に紹介したように,当塾は高校生コースを開講しておりますが,これは大学入試に必要な科目を指導できる教員が揃っているからに他なりません。
当塾で指導できない科目は世界史と地学くらいのもので,先日に世界史選択でご入塾希望のお問い合わせ (新高3生) を頂戴した方は丁重にお断りしました。
これは中途半端な指導になってしまっては申し訳ないからであり,学習のアドバイスもできない状態でお預かりすることが非常に無責任であるという判断からです。
しかし,きちんとした指導ができないにもかかわらず,小中学生指導の片手間,あるいは高校受験対策の延長のような形で高校生指導を行なっている塾が多いのが実情です。
学校から課される課題のサポート,そして学校準拠指導から推薦入試対策,または,カリキュラム等も定めずにちょろっと一般入試対策を行なったりと何でもあり (ただし科目は限定)。
このような状況になるのであれば,高校生コースを開講するべきではないと私は考えます。

当塾は映像による授業を一切用いず,どの科目も対面授業にて行なっております。
先日のブログでも紹介したように,当塾はセンター試験の主要科目はもちろんのこと,東京大・京都大といった難関大入試の二次試験全科目に対応できる教員が揃っています。
当塾は今春京都大の合格者が出ておりますが,二次試験に必要だった英語・数学・国語・物理・化学は,2月25日の前期入試直前まで各科の教員が添削指導および質問受付を担当しました。
合格後,彼は「とても心強かった」と言ってくれましたし,私としても,大学入試に向けてここまでの体制を整えることのできる塾は近隣にそう多くはないだろうと自負しております。
難関大の合否を決するのは,二次試験で求められる記述問題に対応し,解答できる力であることは言うまでもないことです。
しかし,多くの現役生が二次対策は後手に回りがちです。高3生の10月から少しずつ,またはセンター試験後に集中的に実施する等々。
そもそも本腰を入れた受験対策の取り掛かりが遅い,または基本さえも押さえることができていないために二次対策に入れない等,理由は様々です。
そんな中,当塾の生徒たちは余裕を持って二次対策を進めていきます。
先日のブログでも紹介したように,当塾の新高3生たちは高2生の 1年間でセンター試験対策をほぼ完了できている科目が出てきましたから,春から二次対策を開始する科目もあるのです。
センター試験の 5教科 7科目は高3生の春から遅くとも夏の時点でほぼ完成し,以降は二次対策に励むというのが当塾のスタイルです。

大学合格実績ページにも掲載しておりますが,1期生は 6名の在籍で国公立大へ進学する生徒が現時点で 3名 (ほかに 1名が後期試験の結果待ちの状態) となりました。
この 3月から当塾は開塾 2年目を迎え,当塾の指導がより形になる来春からは国公立大・難関大へ進学する生徒数がぐっと増えます。
新高3生は集団指導コース (定員16名) に在籍する半数以上が旧帝大およびそれに相当するところを志望しており,“お手軽なもの” に目もくれることなく日々の学習に励んでいます。
さらに,あと 3年以内には,確実に進路探究塾 Mirai から東京大や国公立大医学部に進学する生徒も出てきます。
進路探究塾 Mirai の高校部は,他塾にはない全科目にわたる難関大の二次試験対策まで可能な対面教育による指導と,洗練された学習空間・質問受付体制を整えています。
大学入試に向けた強い決意のある新高1生・新高2生の問い合わせをお待ちしております。