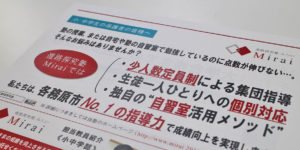先日のブログで高校生の自習室の様子を紹介しましたが,今回は中学生の自習室の様子を紹介したいと思います。
那加中が明日,蘇原中・中央中・稲羽中・鵜沼中が来週に前期中間テストということで,中学生も多くが高校生に負けじと自習室で頑張っていました。
当塾は基本的に中学生と高校生で自習室を分けております。
意図的に中学生と高校生の自習室を集約することもありますが,中学生に気兼ねなく自習室を使ってもらいたいとの思いから日頃は分割しています。

中学生,高校生を問わず,当塾の生徒たちは自習室で黙々と各自のすべきことに取り組んでいます。
自習室には教員を入れておりますが,この教員は決して “見張り” の役目ではなく,生徒たちの質問対応をするためです。
当塾の生徒たちは目的意識を持って自習室を活用しておりますから,自習室で私語をしたり,飲食をしたり,携帯電話に触れたりなどという馬鹿げた行動は取りません。
ごく当たり前のことのように思えますが,他塾から当塾へ移ってきた生徒たちの多くが,当塾の自習室は非常に集中のできる快適な空間だと感嘆します。

当塾の定期テストに対する考え方はいたってシンプルで,定期テストはあくまで『日頃の学習の成果を発揮する場』と捉えております。
ですから,過去問や予想問題をばら撒くとか,直前期に大量に演習に取り組ませるという指導は行ないません。
当塾では,定期テスト前は中学生,高校生を問わず基本的に授業を止め,自習に取り組ませます。
定期テストに向けた学習や準備全般は日頃の自習等で消化してもらうというのが当塾の考え方であり,貴重な授業枠を用いてそれを指導するということはありません。
先日のブログでも紹介したように,当塾では日頃の授業においても各教科とも学校で学んでいるところよりも先行した単元を扱っています。
このことからも,当塾が定期テスト対策指導に励む塾ではないといことがわかっていただけると思います。
ただ,誤解のないように申し上げておきますが,これは中学生の定期テストを軽視しているということではなく,高校進学後に向けた準備の一環という位置づけでこのようにしているのです。
一般的な中学生向けの塾は定期テスト対策指導に力を入れておられ,日頃も学校準拠,または教科書準拠の指導で授業が進んでいくというスタイルです。
とにかく定期テストで得点させること (と高校合格実績) に拘り,ひたすら演習に取り組ませる。過去問をもとに出題を予想し,授業でそれに取り組ませる。
中学生の間はそれで得点できるかもしれませんが,高校生になるとそうはいかなくなります (例外的に高校生にもそういう指導をしている塾があるようですが割愛します)。
高校で学ぶ内容は,どの科目も中学校で学ぶ内容よりも難易度が高いうえに密度も濃いですから,定期テスト直前期だけ集中的に学習に取り組んでも結果は出ません。
つまり『日頃の学習とその積み重ねが物を言う』ことになるわけです。
中学生の頃に定期テストに対して「直前期に頑張ればなんとかなる」とか,「過去問や予想問題をやっておけば大丈夫」などという考えを持ってしまうと高校進学後に修正がきかなくなります。

上記のような考えから,当塾は中学生に対しても定期テスト直前期だからといって教員が用意した問題をやたらと解かせたり,過去問に勤しませたりということを一切しないのです。
生徒たちに “変な習慣” をつけさせるわけにはいきませんし,長い目で見てそれが生徒の成長を阻害することになるということは言わずもがなですからね。
当塾は大学受験まで指導する塾ですから,そんな無責任な指導はできないというのが私たち出す結論です。