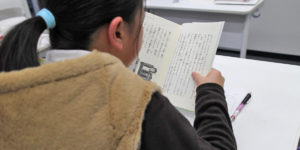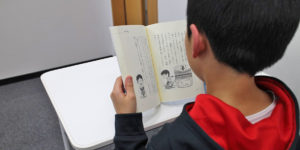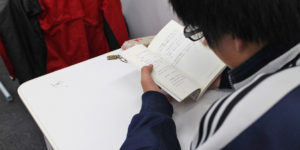昨年の終わりに,文部科学省から大学入試センター試験に代わる『新テスト』の問題例が公表されました。
以前のブログでも触れましたが,『新テスト』では現行とは異なり「思考力」や「判断力」を問い,従来のマークセンス方式に加えて記述式の出題となることが予告されています。
《記事はこちら》
やはり,問題集を解きまくるといった “これまでの学習の仕方” から脱却しなければならないことは明白です。
読書等を通じて教養を育んでおくことや,自身の意見・考えを持ち,それを発信できる力や術を身につけておくこと。こういったことが求められる時代になるのです。
続いて先日,文部科学省は『新テスト』において,導入を検討してきた複数回実施を当面見送る方針を固めたと新聞各社より報道がありました。
『新テスト』は従来の “丸暗記” や “一発勝負” を改めるため,“考える力” を測ることに加えて試験を複数回実施することが大きな柱でした。
しかし,複数回実施は “種々の要因” から実施を 10年程度かそれ以上先延ばしにすることになりましたから,2本の柱のうち 1本が崩れることになるわけです。
複数回実施が難しいということは容易に想像できることです。にもかかわらず,なぜ見切り発車したのか。甚だ疑問です。
さらに,記事には以下のような文言もありました。
「現在 1月にあるセンター試験を複数回にする場合の時期を考えると (中略),12月以前に前倒しされる可能性が高い。そうなると,高校の学習内容が試験までに終わらなかったり…」
これは現制度下でもすでに発生している事象で,ご存知の方も多いとは思いますが,科目によっては岐阜高を含む 5高でさえ,現在の 1月のセンター試験までに終了しない科目があります。
理系科目に関しては特にひどい状況で,5高の中のある高校では物理で数単元が未履修のまま 1月のセンター試験本番を迎えました。
はじめからそういうカリキュラム立てになっていて終わらせる気がないのか,あるいは生徒の独学および塾や予備校頼みなのか。
理系にとっては多くの受験生が数学に次いで要となる科目がこんな状態では,センター試験で好成績を収めることも,ましてや二次や難関私大で合格を勝ち取ることなどできるはずもありません。
それにもかかわらず,多くの高校での進路指導は “国公立大至上主義” の風潮ですから理解に苦しみます。
そういう進路指導をするなら,入試までにカリキュラムが消化しきれない旨を早い段階で生徒たちに伝え,それなりの準備をさせておくべきです。
先日のブログでも申し上げましたが,高校に合格すること,さらには 5高に入学することがゴールではないということがこの点からも明らかです。
たとえ進学校に通っていたとしても,高校のペースに合わせて学習を進めていては大学入試で勝つことはできません。これは現制度下でも,『新テスト』導入後においても同様のことが言えます。
当塾の集団指導コースでは,科目を問わず遅くとも高3生の 7月には終了するカリキュラムで指導していますから,以降は演習を通じて知識・理解の定着を図ることが可能です。
このことからも,以前のブログでも申し上げたように,私はろくに学習をしてこなかった生徒に対して「高3生の夏からが勝負だ」などとは口が裂けても言いません。
高3生の夏までにコツコツと準備 (例えば英語科なら4,000語レベルの英単語やイディオム,文法事項) を進めてきたうえでの「勝負」なら話は別ですが。