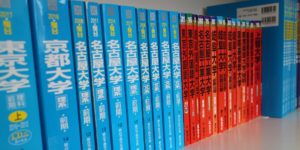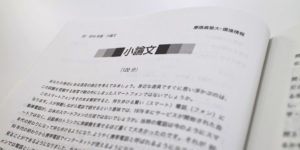高校生の前期中間テストが落ち着き,徐々に結果が判明しつつあります。
当塾は定期テスト対策指導,例えば過去問や予想問題に取り組ませるといった “付け焼刃” 指導を一切行ないませんが,当塾の塾生たちはなかなかの結果を残してきます。
写真は岐阜高に通う高1生 (中央中出身) のもので,数学 A が 100点,物理基礎が 99点という結果を残してきました。
他の生徒からも数学 I で 100点,物理基礎で 100点などと良い報告を受けておりますが,当塾は定期テストに特化した対策指導は行なっておりませんから,生徒たちの頑張りが結実したのみです。
当塾は定期テスト直前前は通常授業を止め,自習と質問受付を行なうに過ぎません。
定期テスト前,集中的に学習に取り組むのは当然のことですが,それが定期テストのため “だけの” 学習に陥ってしまっては大学入試で勝負することはできません。
大学入試や将来を見据えて日々の努力を怠ることなく,その積み重ねをもとにして “定期テストでも得点できる” という状態が望ましいと私は考えます。
私はよく高校生に,「定期テストの結果にこだわり過ぎる必要はない」と話しています。
たとえ結果が芳しくなくとも,「入試に必要となるであろう科目の復習はきっちりやるように」と伝えるにとどめています。
昨春,京都大に現役合格した教え子も,高1生の前期中間テストの成績表を見ると合計点の学年順位が 273位 (400名中) という結果でした。
また,およそ 1ヶ月後に受験している進研模試においても,彼の英⋅数⋅国 3科の学年順位は 275位 (400名中) という結果でした。
つまり「定期テストで高得点 (または 進研模試で高得点) = 大学入試で結果を残せる」という図式が成立しないということが,この成績結果からもよくわかります。
定期テストや各種実力テストで結果を残すために,過去問や予想問題に縋って上辺だけの結果を繕うことに意味はないということです。
眼前のことだけに追われず (追わせず),長い目で見た学習に取り組む姿勢が,当塾の塾生たちが高い合格実績を残せることにつながっているのです。